
家族に囲まれるさいごの時間を生み出したたった一つの決断【看取りの報告書・BYさまのこと】
かわべクリニック院長の川邉正和です。私たちは、患者さまが最期の時間をどのように過ごされたかを「看取りの報告書」としてまとめています。今回は、BYさまのご様子をご紹介いたします。
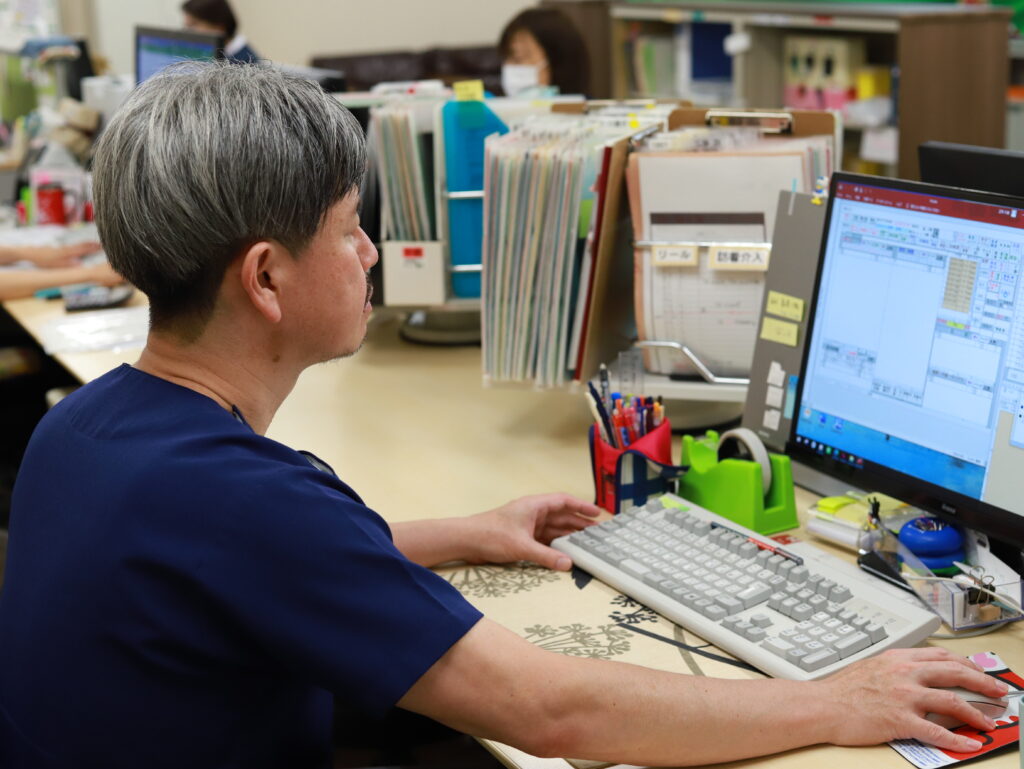
いつもお世話になっております。貴院から退院されたBYさまについてご報告させていただきます。
退院直後から、ご主人やお姉さまに加えて、介護休暇を取得して東京から帰宅された息子さんに囲まれていました。さらに数日後には勤務を終えて休暇に入った娘さんも加わり、終始穏やかなご様子でした。ご本人もご自宅に戻ったことに気づかれ、笑顔や発語も見られました。
BYさまはかつて看護師としてご活躍されていましたので、看護師時代の仲間から清拭などのケアを受けられ、部屋には励ましの色紙が飾られていました。「看護師さん!」と呼び掛けられると、はっきりと開眼し、視線を追わせる様子は私たちにも印象的な出来事でした。「仕事に一生懸命でがんばり屋さんだった」とご家族が振り返っていた人となりが伺える、療養の日々だったと思います。
貴院での治療方針に準じ、脳の腫れを抑えるステロイド薬(リンデロン4㎎)の投与を続けたほか、2日に1回は頭部に埋め込まれた器具から脳の圧力を下げるために脳脊髄液を30ml排出する処置を継続していました。
数日後、意識レベルの低下、腫瘍熱と推測される発熱がありましたが、懸念していた嘔吐、硬直、痙攣などの症状は幸い出現せずに経過し、翌月のある朝、ご家族に見守られながら静かに永眠されました。
厳しい病状の中で、自宅看取りを決意されたのは娘さまでした。お母さまとともにご本人も看護師である娘さまには、医療者ではなく一人の子ども、家族として過ごしていただけることを心がけました。永眠の確認に伺った際には「あと少しでも退院が遅れていたら、お母さまは自宅に戻ることができなかったかもしれません。あのタイミングで退院を決断されたからこそ、ご家族で過ごす最期の時間が実現できたと思います。英断でしたね」とお伝えしたところ、娘さまは涙を流されました。
入院中の貴院での意思決定支援、多方面・多職種からのサポートがあってこその、娘さまの決断であったと思います。BYさまを支えるその一員として、私たちを加えていただきましたこと、心より感謝申し上げます。
この度はご紹介ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
呼吸器外科医として、そして在宅医として10年、多くの患者さまの最期に立ち会ってきました。その中で最も重要だと感じるのは、「意思決定支援」の質が、看取りの質を大きく左右するということです。
BYさまのケースで特に印象的だったのは、退院のタイミングでした。脳転移による症状は日々進行し、医学的には「あと数日」という状況での退院でした。呼吸器外科医としての経験から、肺がんの脳転移がどのような経過をたどるか、私には予測がつきました。だからこそ、「今このタイミングを逃せば、自宅に戻ることは不可能になる」という判断を、ご家族と共有する必要がありました。
しかし、医学的判断を一方的に押し付けることはできません。患者さまやご家族が「延命するかどうか」「在宅で過ごすかどうか」など、深刻で複雑な判断を迫られます。こうした中で、医療者には複数の選択肢をわかりやすく提示し、本人と家族の価値観や希望を丁寧に汲み取りながら意思決定プロセスを共に歩む支援が求められると考えています。
終末期における意思決定支援については、国内外で多くの研究がなされています。
欧米を中心としたシステマティックレビューでは、意思決定支援ツール(Decision Aids)を導入した場合、患者や家族の治療選択の理解度が向上し、価値観に即した判断が行われやすくなり、侵襲的治療より緩和的ケアを選択する割合が増えるという報告があります(Cochraneレビュー/86試験、115試験)。
終末期ケアに特化した意思決定支援ツールを対象としたレビューでも、選択肢への理解促進と質の高いコミュニケーションの向上が報告されています。
また、高齢者の在宅療養・看取り場面において、意思決定支援が「自宅での看取り」を可能にする鍵となるという国内研究も報告されています。(日本在宅医療連合学会)
娘さまには医療者としての知識があるがゆえに、かえって迷いも大きかったと思います。「もっと積極的な治療をすべきでは」「苦痛緩和は十分か」といった医療者としての視点と、「母のそばにいたい」という娘としての思いの間で揺れ動かれていたのだと推察します。そこで私たちは、医療的なことは私たちに任せて、娘さまは娘として過ごしてもらいたいと考えました。
専門的なケアは医療者が代わりに行えますが、家族としての時間を過ごせるのは家族だけだからです。
今回の看取りを通して、意思決定支援の真価を改めて実感しました。 それは、患者さまとご家族に「自分たちの選んだ道で良かった」と思っていただけるような支援をすることです。
私自身、在宅医療に携わって10年。病院では救えなかった「大切な何か」を、在宅医療では守ることができると感じています。それは、患者さまの尊厳であり、家族の絆であり、「自分らしい最期」という願いです。
BYさまの穏やかな旅立ちは、適切な意思決定支援と、タイミングを見極めた医学的判断、そして家族の愛情と勇気が結実した結果だと捉えています。
娘さんの勇気ある決意は、結果としてご本人がご家族に囲まれ、安らかな最期を迎えることにつながりました。これは当事者だけでなく、病院での丁寧な説明や多職種連携による支援、そして「娘として寄り添いたい」という思いを尊重する姿勢があったからに他なりません。
在宅医療に携わって10年。私たち医療者にできることは、ご本人やご家族に寄り添い、選択の背景にある不安や希望を理解し、どの選択肢を選んでも支えていくという姿勢を持ち続けることです。 意思決定支援は単なるプロセスではなく、患者さまと家族が尊厳を保ちながら人生の最期を過ごすための大切な「橋渡し」なのだと強く思います。
今後も、東大阪プロジェクトの一員として、一人ひとりの患者さまやご家族が納得のいく選択をできるよう、温かく寄り添い続けたいと考えています。
最新の記事
ハッシュタグ